今日は教育のトライのお話。

少しの背伸び
利用者の担当であっても、事業所の決まりを作る場面であっても、関係機関と連携をとる場合であっても、職員に対して少し難しいかな、でも背伸びすることで届きそうだな、と言う課題を与えることがあります。
インシデントの振り返りを行い、事業所のみんなの意見を取りまとめて、作業手順を作成する、関連のある文書を集めて抜粋して事業所のマニュアルを作る、そんな課題であったりもします。
プレゼンテーション資料を作成する、稟議書やマニュアルを作成する、そんな業務が医療従事者には限られた人以外はあまりない業務なのかなと思います。
ですがその中には、自分がその事象に関してどう考えるか、多面的に見てリスクを把握し、それを回避する術を検討するか。国が公表しているガイドラインに基づきながら、事業の特性、事業所のルールや業務内容を考慮しながら作成していくかはなかなか難しい作業であり、根をあげる職員も実は多かったりします。
もちろん通常の訪問業務もあるため、期限は決めず、じっくりとその仕事に向き合ってもらうことが多く、何度も修正を繰り返しています。
完成を目指さない
上記の仕事は人事考課内で訪問件数とは別途で評価する項目となっています。
なので、課題を伝えると目標に「12月までに完成」と記載する職員も多いのです。期限を決めてそれに向けて着実に進める、そして提出し、完成をする、それがもちろん理想の仕事の仕方なのだと思います。
その点について私は「仕事を完成させることが目標なのではなくて、その仕事をあなたが経験することで、成長することが目標なんだよ」と説明します。
仕事をすることではなく、仕事を通して自分自身を成長させて欲しいと思っています。完成ではなく、自分は何をどう考えて何を思ったのか、そして何を調べ、何を疑問に思ったか、そしてそれをどう解決し、自分の中に取り込んだか、そのステップが非常に重要なのです。
もちろん仕事なので完成は絶対条件です。何年もかかるということも論外です。ですが、ただ完成させればいいかというと、そう言うものではないのです。
事業所の一職員としてその事柄を学んで、どう成長したのか、その成長した姿を期待して仕事を渡しています。
それで何を学んだか
同じ仕事でも、創造性の高いものは特に差が出ます。それは個々の特性に合うように答えの明確なもの、自分が一番体験していること、周囲の人に意見を求めながら作成していくものと、振り分けています。
私から見ての適性や将来像で選んでいるので、本人としては戸惑うこともたくさんあります。根をあげることもありますし、辛い思いをすることもあります。
ですが、私は何度でも添削しますし、どうしたらいいのかという取り止めのない相談にも乗ります。必要資料も渡しますし、参考文献も紹介します。やらないからと言って叱責をすることはないし、急かすこともしません。
その仕事と向き合おうとするタイミングが来ることも自分と向き合うと言う成長の一端です。やらなきゃいけないけど、分からない、聞いてみようか、時間あるのにやらないのはこの仕事から逃げているんだろうか、どうして自分はこれが分からないのか、そうやって自分に問いかけていくことも大切な仕事の時間です。
確かに私がやった方が速い仕事もありますし、そう言われることもあります。けれど、完成だけが目標ではないのです。管理者に聞けばなんでも分かるよ、なんて事業所は私が抜けたら終わりです。それでは経営的にも望ましいとは言えません。
その仕事をすることで事業所としても盤石になりますし、組織としての発展の土台になります。
けれど、そもそもの根幹は職員個々の能力の向上であり、目標は職員の成長なのです。それをなくして組織は成長できません。そして、その職員の成長をどれだけサポートできるかも、私の成長なのです。
できることをできる人が、できるようにやっていたら成長は望めません。等身大の自分も素敵ですが、伸びていく職員の姿には感動しますし、私自身も常に向上していきたいと思うのです。
なので少し背伸びをして、ギリギリ届くラインを行っています。でも、私のギリギリ届くラインは、私が決めることはできず、残りは全部私の仕事なので、ジャンプしても届かないこともあり、自分が負傷する時もあります。気をつけます。
そんな私の根拠のない、教育のトライのお話、でした。
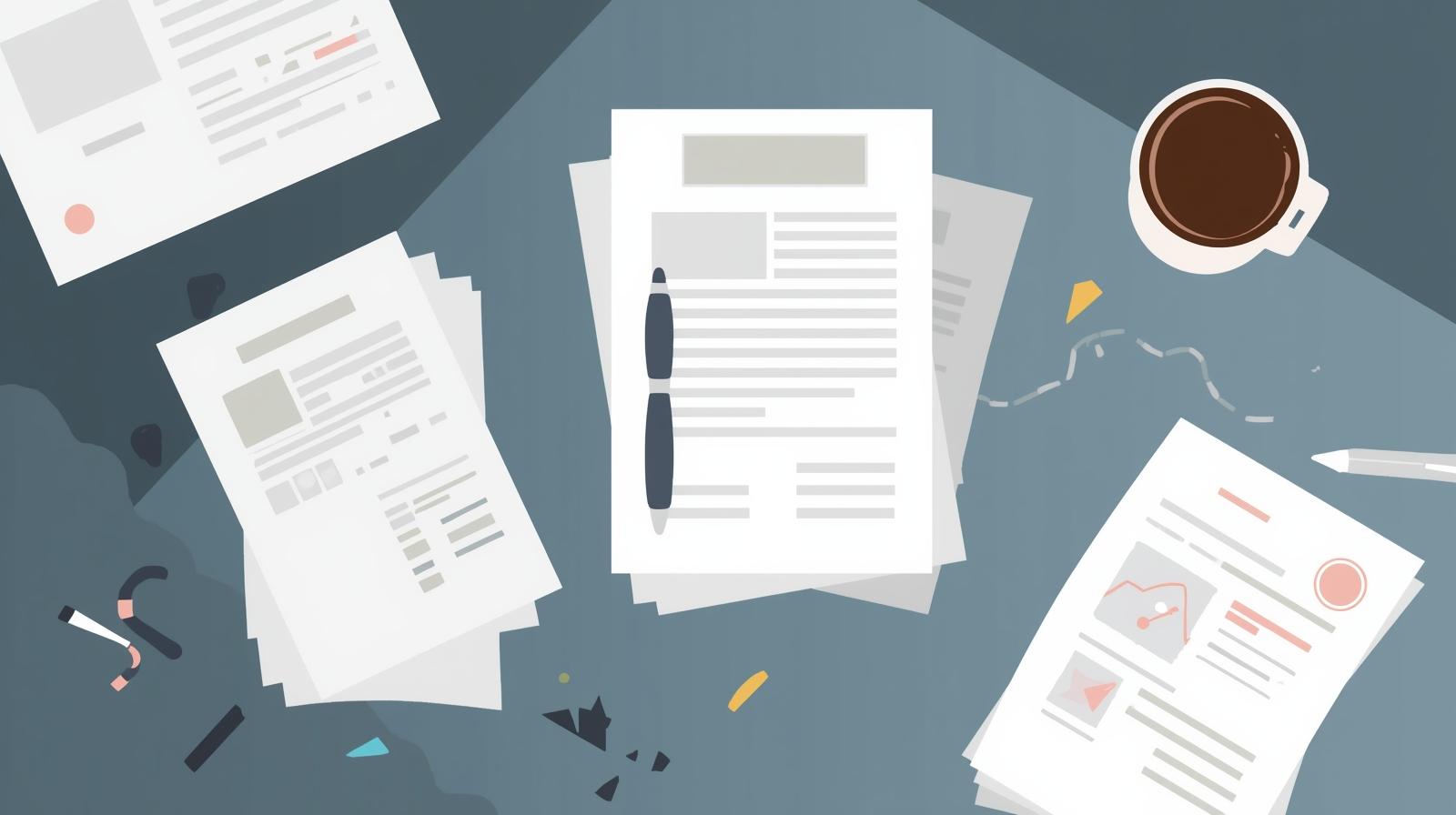


コメント