今日は精神というくくりのお話。
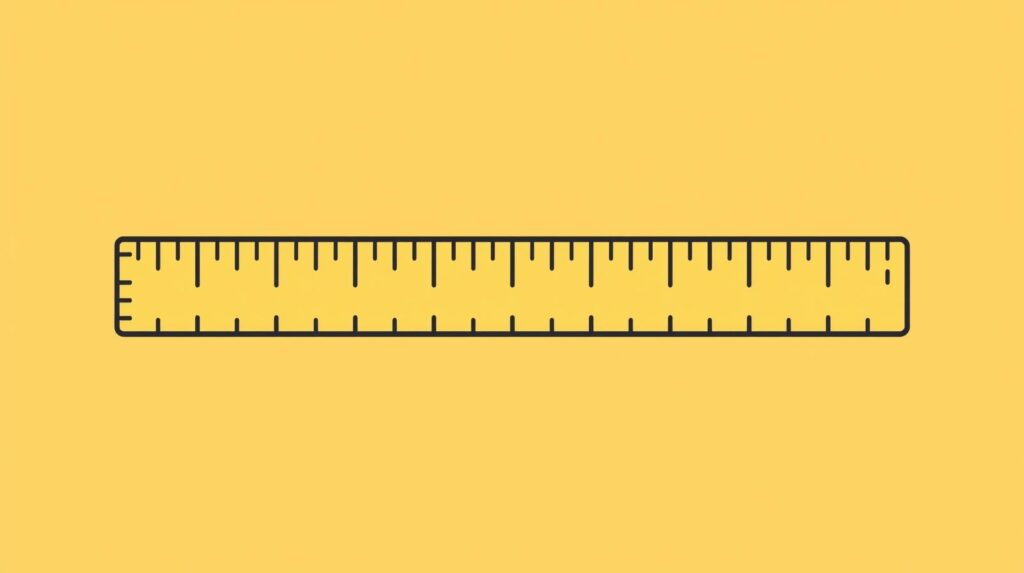
どう接していいのか
精神科訪問看護での利用者さんもだいぶ年齢層が低めになってきています。訪問看護を提供している職員の世代と、10代の若者達であると、なかなか抵抗感がある職員が多かったりします。
10代で精神疾患を診断されると言うことは知的障害や発達障害であったり、もちろん統合失調症、うつ病、気分変調症などさまざまな病気に罹患しています。
それに加え、親からの虐待や不理解、集団生活でのいじめ、貧困や周囲との不協和、トラウマティックな体験など、多くの要因が加わり、その末に訪問看護という資源にたどり着いています。
その衝撃を受けた出来事を体験した時期が今と非常に近いことが多く、むしろ現在進行形であったりするので、精神的にアクティブな症状を呈していることも多いのです。
そんなアクティブで、すぐに対処しないと生命の危機を感じるような症状を呈しているというだけでも、介入には緊張が走ります。
自分とは全く異なる社会で生きている利用者さん、でも自分と比べて半分程度の人生の経験値の人に何を伝えて言ったらいいのかと困惑します。注意深く接しないと、と思わされる条件揃いの利用者さんに戸惑いを感じるのも仕方のないことだと思います。
一緒に遊ぶことのできるちびっことは異なり、大人にはなっていないけど、でも心も体も大人に近づいていく成長段階の中で揺れ動いています。そんな中、急激に変化していく姿を整えながら共に歩んでいくのは、責任重大感もありますし、大人しく加療を受ける間もなく、活発に社会に接していっては衝撃を受け、行動化していく方も多いので、介入としてはかなり忙しめになります。
目標や行動はコロコロと変わり、目標に対して整合性のない行動が伴ったり、社会的に正しい行いでなかったり、なぜそれを選択したのかと訳が分からなかったり、こちらが混乱することも多く、あえてこちらを混乱させたり、相対する感情を激しく表現してきたりと、どうしていいものか…と途方に暮れることも多々あります。
社会としての正しさ
彼らは社会という壮大なものに苦しめられていることが多いです。それは世代は問わないものですが、自分が10代の頃も多かれ少なかれそうだったのかと思います。
「常識」「普通」「当たり前」そんなみんなが使っている暴力に苛まれてきているのです。
普通は決して平均値ではないし、難なくできるものではありません。ですが訪問看護に勤めている職員は国家資格を取得していることが大前提ですので、それらを苦しみながらもこなし、乗り越えてきた人達ではあります。
そうなると自分に染みついた常識を無意識下に使って話をしてしまうことがあります。けれど若年の利用者さんはそういったことに傷つけられている真っ最中です。
そんな中で、親や病院の方々、行政や学校、そんな人達にも社会の常識を見せつけられ、さらに訪問看護も加わるとなると、はて、訪問看護とは?という立ち位置になってしまいますね。
同じ役割の人間は多数いるのに、さらに参加者を増やす意味はなんなのかと考えなければいけません。親の相談に乗ることや、内服を飲めているか確認するなどの保護者や病院から見た役割は別にして、ですが。
そんな苦しめられている彼らを苦しめる訪問看護は必ず終了になります。その時に「やっぱり分かってくれなかったね」「あの経過からいったらしょうがないよ」と考え、自分達を守ってあげてしまえばこちらはそれで終わりかもしれません。ですが彼らの人生は、また一人、敵が増えた社会でさらに生きていかなければならないのです。
苦しめられていたのは誰?
頭では分かっていて、精神科のケアの知識もあるにも関わらず、そんな常識を押し付けてしまうのはなぜなんでしょうか。
確かに本人の言うとおりにしていてはことは進みません。ですが常識を押し付けても事が運ばないのは明白です。
それでも常識や当たり前を伝えてしまうのは職員自身がその「常識」に縛られて苦しめられてきたからであると思います。
挨拶はきちんとする、宿題は忘れずやる、遅刻はしない、食べる時にはいただきますと言う、そんな当たり前のことから、メールの最初は平素よりお世話になっておりますをつける、畳のヘリは踏まない、名刺は相手より下から渡す、なんてものまで。
当たり前として社会のルールとして強要されるものを「仕事ってそう言うもの」「上司なんてそんなやつ」と、子供の頃の辛かった思いをたくさんの諦めと共に手放してきたからなのだと思います。
それらに歯向かって、苦しんでいる若年層の利用者さんに「わがままだ」「そんなんじゃやっていけない」と思うのは、たくさんの気持ちを押し殺してきた自分を守るための防衛統制でもあるのです。
超えてきた自分で話をすると、こちらの反発心が出現してしまいます。それは利用者さんのケアではなく、自分という人間の尊厳を守りたいがための行動です。そのままでは必ず不協和は起きます。
そんな時のアドバイスとしては「17歳の利用者さんと、17歳の自分で話してみて」と伝えています。私たちは子どもではない、ですが、子どもであったのです。
大人になった人たちは、必ず、子どもベテランですから。だからこそ、共に歩んでいけるはずです。
そんな私の根拠のない、精神というくくりのお話、でした。
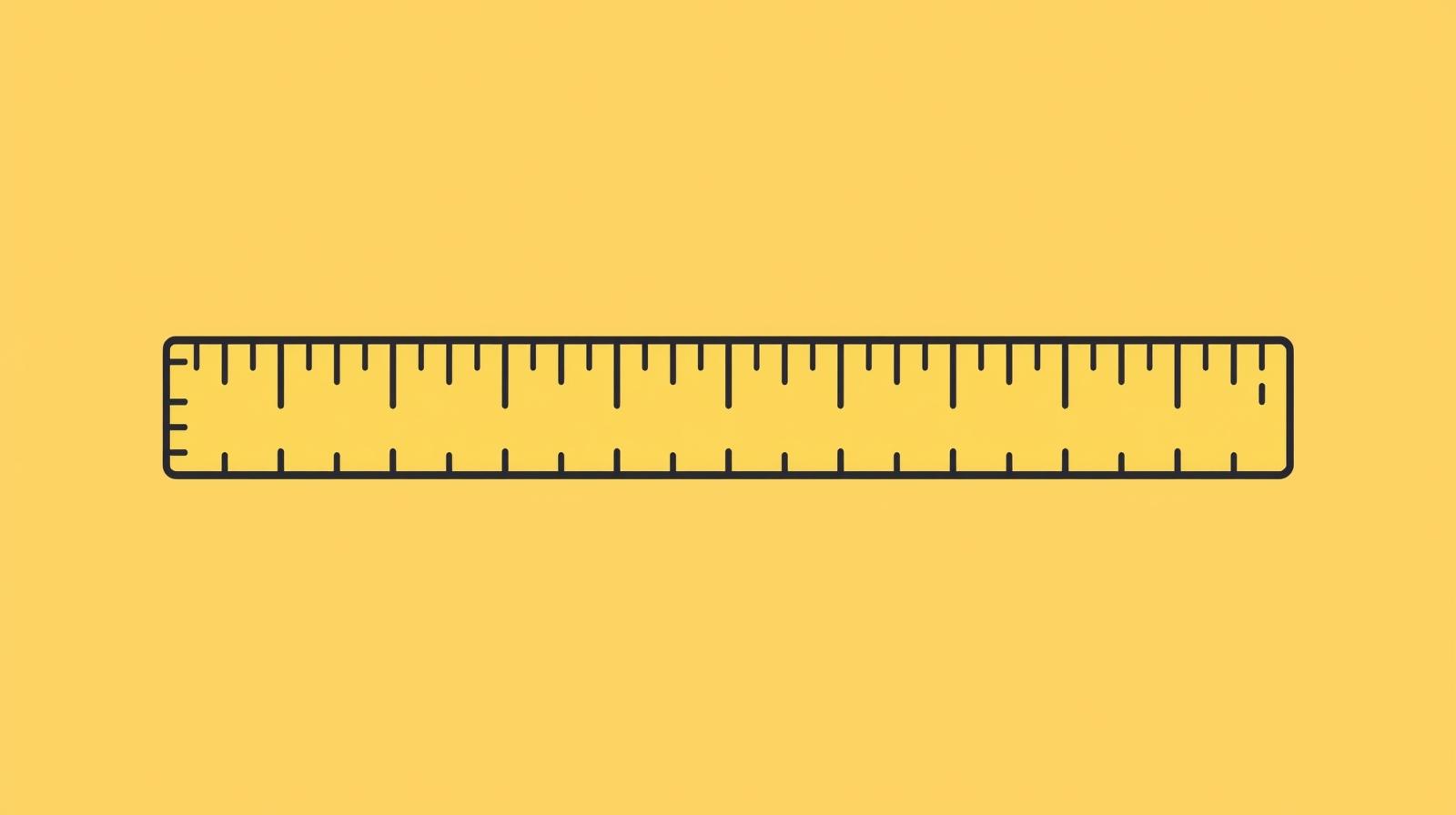


コメント