今日は精神というくくりのお話。
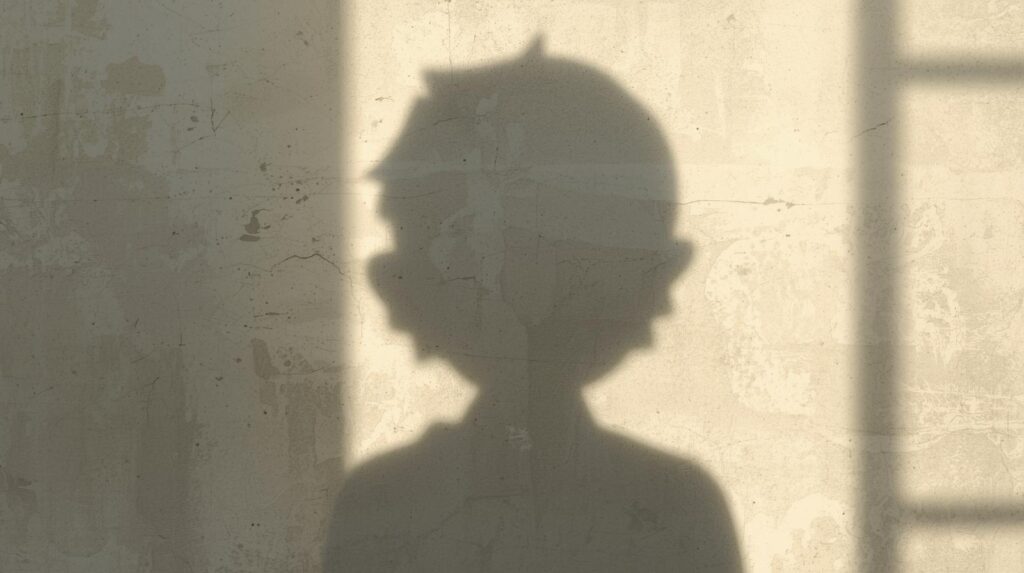
驚きと怖さ
幻聴や妄想への反応として独語を呈する方がいます。
側から見れば何か対象もなく、何の音もしない、そんな場で一人話している姿か異様に映ると思います。
時には淡々と、時には感情豊かに話される人もいます。突然泣き出し、膝から崩れ落ちるようなこともあります。そんな方々を支援する人は医療従事者ばかりではありません。
ヘルパーさんや、グループホームの世話人さん、コンビニの店員さんや役所の方々、研修を受けていたり、学習をしてくれている方もいれば、何も知らずに突然目にすることもあるかと思います。
グループホームの世話人さんは初めて精神疾患の方に接することも多く、介護施設で働いていた方がいても、障がい福祉のベテランです、というよりは食事を作る仕事につきました、というような形で働いている方が多い印象です。
そんな中で世話人さんが目にする独語という明らかに目にみえる行いは戸惑いを覚えるには十分な行動なのかもしれません。
「どう接したらいいのか分かりません、どうしたらいいですか」「怖いんです、一人でずっと話しているし、なんとかやめるように言ってください」なんてご相談を受けることもあります。
だいぶ大きなリアクションのものになると、側から見ても驚くし、本人からしたら順序があるものでも、周りからすると突然の感情爆発なので怖さを感じる方がいるのは当然の反応だと思います。
そうなった時に世話人さんはどう接したらいいか分からない、怖い、は当たり前の反応です。
その時は「怖いと思っていいです。戸惑うということを本人に伝えてみてください」と話をしています。
社会とは何か
医療従事者は精神疾患について学び、その上で訪問看護を行なっています。
そんな人間が世間にどれくらいいるかというと、だいたい病院の中にしかおらず、人口のうちのどれくらいかと言われれると「やっぱり看護師さんってすごいんですね」とどこに行っても感心されるくらいの少なさです。
ですが、それが社会というものなのです。
精神疾患の人に偏見がある、一人で話している人が怖いと思う、自分が危険に晒されるのではないかと考える、それは綺麗事だけではない当たり前の社会です。
今の周囲の環境だけをせっせと作り上げても、必ずそこから出なければならない時がきます。訪問看護へ「こう言ったんですか」「こういう風に話してください」「この話はしないように」と指摘をいただく支援者さんもいます。ですが、その理想形をいつまで作り上げていくのでしょうか。
100%最適な療養環境はありません。それよりさらに、100%理想郷の社会はないのです。
歪なままの世界
守ることはとても大切なことです。不用意に傷つくこと、謂れのないことで差別を受けることは避けたいのはもちろんです。
ですが社会はそれほど統率されたものではないのも事実です。
恥ずかしいことは恥ずかしいと、怖いことは怖いと、おかしいことはおかしいと、今のうちから伝えることは、私は愛情だと思っています。
それはもちろん、こんな楽しいことがあるよ、面白い世界だよ、理解してくれる人はここにもいるよ、と伝えることも合わせて行います。
社会は歪だからこそ、思わぬところで乱反射が起き、きらびやかに光り輝くものだと思っています。
それは見た目だけ綺麗に繕わなくても、信じて送り出す、そして一緒に楽しむことが大切で、いいことだけの世界はないと自分自身も知っている世界をそのまま一緒に体験していく同士でありたいと思っています。
心配なのはもちろんですが、信じる、信じておかしいことは伝える、楽しいことも伝える、それが一番最初に関わる社会としての訪問看護の責任だと、私は思っています。
そんな私の根拠のない、精神というくくりのお話、でした。


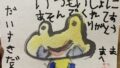
コメント