今日は精神というくくりのお話。
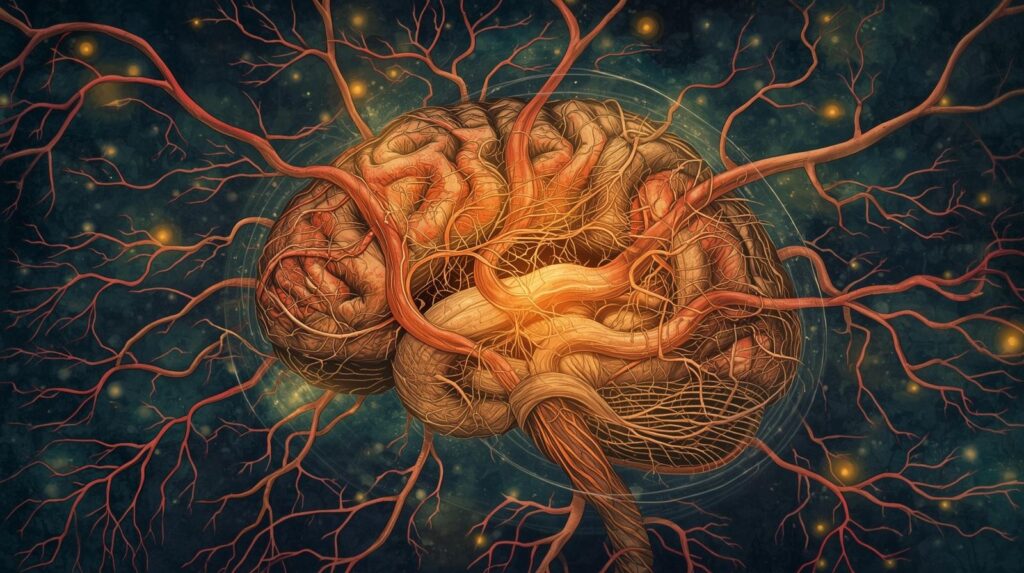
一般科と精神科
総合病院にしか勤めたことがなかった私は精神科という学問に触れた事がありませんでした。訪問看護で初めて精神科の看護師さんと出会い、精神科では精神科以外の診療科目が「一般科」と呼ばれていることを知りました。
一般?一般的な科ってこと?一般的とは?放射線科とか、代謝内科とかあんまり馴染みがないものでも身体のことであれば一般と呼ばれるの?どういうこと?ととても困惑しました。
身体を見ることは一般で、精神を見ることは一般ではない?一般じゃなければなんなのか、え、特殊なの、なんでそんな括りができたのでしょうか。
私は精神科を精神科としか呼んだことはなかったし、身体を見ることが一般的とも思いませんでした。でも確かに精神科を併設していない総合病院は多いのか、400床以上ある病院に勤めても「精神科の人は外来のみで入院施設はありません」「精神科は院内に入院している方だけです」と言う括りがありました。
それを当たり前だと思っていたのは自分です。あれ、一般科と言わせているのは誰なんでしょう。
他の科の看護師さんは精神科が同じ病院に外来でも入院でもないことを普通だと思っています。さぁ、それを思わせているのは誰なんでしょう。
知らないうちに多数派は少数派を追い詰めているのかもしれません。自分が多数派だとも知らず、相手がこちらを一般的だと言っていることも知らずにいます。それが無知であることは理由にならないけれど、看護学校の精神科の科目は、そんな区別を教えてくれたのでしょうか。
たぶん教えてくれていました。老年期、青年期、小児期で括られた年代により分けられた身体的な病気の実習と「精神科」という別の科目の実習がありました。その時ですら、いつも実習に行っている病院に精神科はない、精神科は精神科という病院がある、それに気づかなかった私は無知であるより先に、区別ではない差別を当たり前にしていたのかもしれません。
精神科は総合病院の「総合」の中に無いのです。「精神科もある総合病院」の中には精神科はあるのです。精神科あるのに他の科もあるんだ、へーそんなところもあるんだ、そんな思いでいたのかもしれません。
脳という特別な臓器
お腹の調子が悪い、食べるとムカムカする、そんな状態を友人が訴えたとしたらどうでしょうか。
「胃が悪いんじゃない、病院に行ったら」と声をかけるのではないでしょうか。胃が悪いとしたら内科かな、消化器科かな、近くに評判のいい病院あるよ、ここ口コミいいよ、なんて調べて伝えたりするかもしれません。
最近イライラして夜眠れない、よく分からないけど、いない人の声で悪口を言われている声がするんだ、そんな状態を友人が訴えたとしたらどうでしょうか。
「頭が悪いんじゃない、病院に行ったら」と声をかけられますか。
頭とはおそらく脳という臓器を指していて、なぜかその臓器だけは病気や臓器の一つであるという概念を飛び越えて「その人自身」であるという認識を持ってしまいます。
「頭が悪いね」は悪口で、「胃が悪いね」は心配している発言になるのです。この認識の差が精神科医療への偏見なのだと思います。
いつも精神科が初めての訪問看護入職者さんに同じ説明をします。
利用者さんに「心臓が悪いんだ」って言われたら「それはどうして言われたの。胸にテープを何個も貼って、検査をしたことはある?腕から管を入れて、心臓の血管を見たことは?ジェルを塗られて、超音波で検査した時に言われたのかな」と聞きますよね。
心臓が悪い、それが不整脈なのか、冠動脈疾患なのか、弁疾患なのか考えますよね。
それが分かった経緯や行った検査、入院歴や、手術痕の確認、お薬手帳を見せてもらって、心音や血圧、脈拍測定で確認をします。「どんな」心疾患なのか、その病気の管理のためにどんな注意が必要なのかを調べます。
でも、利用者さんに「手を洗わないと自分を許せないんです」と言われたらどうでしょうか。
「そっかー…」の続き、考えつきますか?
手を洗わないと自分を汚いと感じるの?それはおかしいと思っていてもやめられないの?そうしないと許してくれない神様がいるの?そう聞いてくれる看護師さんは非常に少ないです。
PTSDかな?強迫性障害かな?統合失調症なのかな?「どんな」精神疾患なのか、それを聞かずに適切な対処はできるのでしょうか。
「どんな」心疾患なのか分からず対処はできないのと同じで、心疾患に合併してくる病気もあります。
「どんな」精神疾患なのか分からずに、見ていることはないでしょうか。それに複合的に合併してくるものが何か、それで分かるのでしょうか。
病気とは回復過程である
ナイチンゲールは「病気は回復過程である」という考え方を示しました。
高血圧は塩分や脂質を摂りすぎながらも、それでも臓器に血流を届けたいという身体の機能からくる病気、のように、うつ病は自分に厳しく、感情を押し殺して我慢してきたけど、もうそんな生き方じゃ耐えられない、動けないという脳の機能からくる病気だ、というような解釈を私はしています。
どんな病気であっても、その人の生き方の結果です。
糖尿病の人に「糖分はあまり摂らないように、カロリー制限は守ってください。運動習慣を身につけてください」だけではあまり良くなりません。
糖分を摂りたくなるのはなぜなんだろう、不規則な生活は仕事が合ってないんだろうか、食べることでストレスに対処しているのであれば違う対処方法を見つけてもらわないと、栄養の重要性が分からないなら理解できるような伝え方で栄養指導をしなくては、と考えて介入しないと難しいですよね。
うつ病の人に「朝起きて、朝日を浴びるようにしてください。規則正しく過ごして、楽しいと思うことを見つけて、夜はちゃんと寝てください」だけではあまり良くなりません。
仕事ではどんなストレスを抱えていたんだろう、その時にどう考えて対処していたのかな、自分を責める思いはあったんだろうか、周りに相談できる人はいたのかな、幼少期から弱音を吐くことや途中でやめるような事がダメだと思い込んできた発達過程があるのかな、と考えて介入しなければ良くなっていなかないのと同じことです。
では朝7時には起床、必ず1回は外出して、楽しいことだけ考えていきましょう、夜は21時には寝る、薬出しておくのでそれ飲んでください。それでできたらすごいですよね。
どの本だったのかすっかり忘れてしまって、私自身もその本をも一度読みたいくらいなのですが「精神科患者の妄想や幻聴は、芸術のようなものである。その社会に自分の脆弱性や信念、感情や思いがどうにも適合できず、その末にそれでも適合しようとして鳴らした音楽のようなものだ。」みたいな文章があったんです。
多分結構違うんですけども、もっと美しい文章だったはずなんですけども…すいません。
それを読んでから「病気」の概念がだいぶ変わりました。この人はどんな社会が辛くて、それでもここで生きていこうとした末にどんな音楽を鳴らしているんだろう、と耳を澄ますようになりました。
それは身体、精神関係なくその人の生きてきた中でできた偏りを回復するための過程に病気があるのだと考えています。
それは病気があるなしに関わらない「人をみる」ということなのだと思います。
そんな私の根拠のない、精神というくくりのお話、でした。
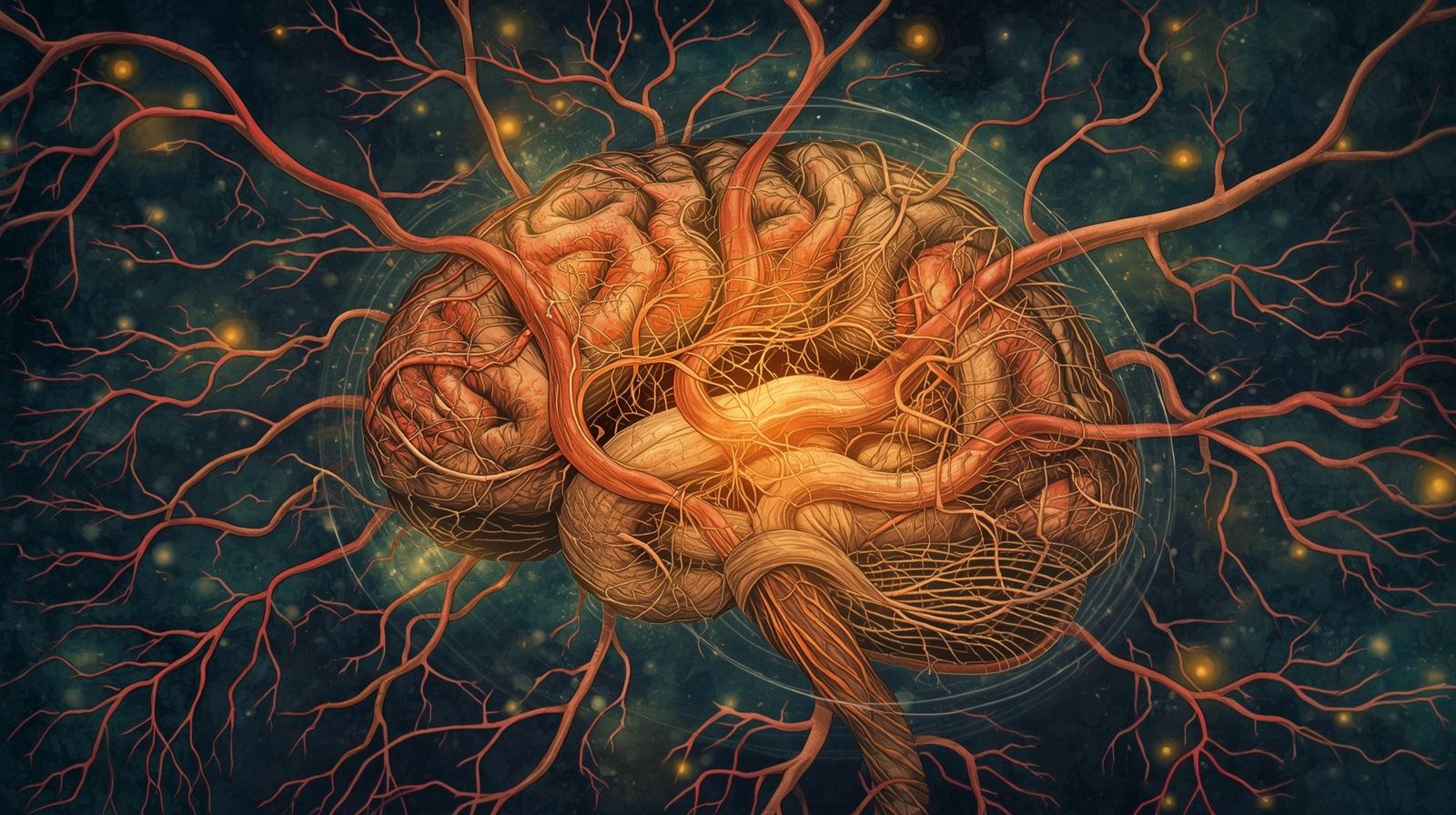


コメント