今日は教育のトライのお話。
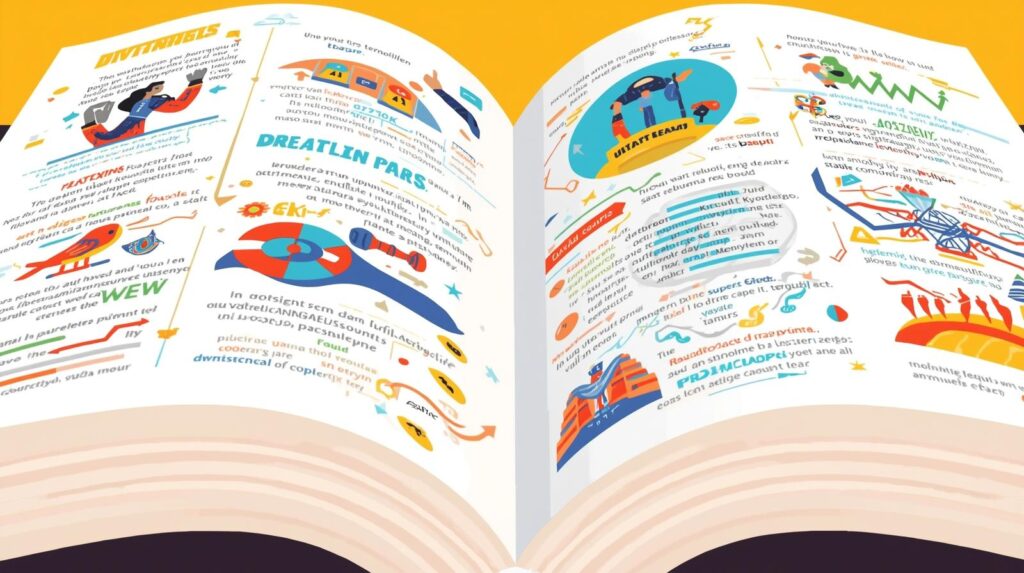
知識って何。
医療従事者としての専門知識や、訪問看護職員としての算定の知識、たくさんの知識を披露する場が訪問看護にはあります。
利用者さんに内服薬について説明する、ご家族に今後の状態変化についてお話する、ケアマネージャーさんに制度の紹介をする、病院の事務さんに利用者さんの状態報告する、などです。
その相手が何の知識を持っているかは不明瞭なことが多いです。
利用者さんが薬剤に関して書物を多く読破しているかもしれないし、ご家族が介護福祉士として長年施設に勤めた経験があったり、看護師を娘さんにもつケアマネージャーさんだったり、訪問診療に長年勤めていた事務さんだったり、というような感じです。
多く知識を持っている人もいれば、全く持っていない人もいる。それは利用者さんのように基本情報にまとめられていることはなく、話をしていくうちにこちら側がどう伝えていけばいいのかを判断していく必要があります。
こちら側も、もちろん持っていない知識も多数あったりします。でもそれを「全く分からない」と伝えるのではなく、自分なりに説明し、理解を促し、相手に「分かった気持ち」になってもらえるよう立ち振る舞うことも時には重要です。
本当に分からない場合は後ほど管理者に連絡し、「今度の訪問でお伝えします」も、とても誠実でいい対応ではありますが。
必要なのはパフォーマンス力
訪問看護に必要な能力は何か?と聞かれたら、私だったら迷わず「パフォーマンス力」と答えます。
これは在宅だから必要か、というと病院に勤めていても同じなのかなと思っています。
急変したことを分かりやすく伝えて人に集まってもらう、自分が分からないことを明確に伝え、サポートを依頼する、仕事が終わらないのに委員会に行かなければならず、もうどうしようもないと助けを求める、などたくさんの場面で自分の能力、状況、思い、魅力、苦手分野を周知し、人を集めて惹きつけるという能力は重要です。
自分が理解している知識を専門用語を並び立てて伝える、医療従事者でないと分からないのでと切り捨てる。そんなことをしてくる人間に自分の人生に関わって欲しくないと思うのはもっともだと思います。
医療従事者というマウントをとって、上からものをいう医療従事者の方は以前よりは少なくなってはいるのでしょうが、やはり耳にすることもあります。
新規依頼をいただくときも「ちょっと言い方が強すぎるのでまいってしまったみたいで」「穏やかな看護師さん、そちらにいますかね」「あまり相談にのってもらえず決めつけられる事が多いようで」とそっと苦情を聞いたりします。
人を惹きつける力、これ以上に必要なものはないと思います。ではそれをどうやったら身につけられるのか。というと言うなれば「人間力」になってしまうのですが、それは長期にかかることではあるので1on1ミーティングを通して高めたりしますが、同時並行でパフォーマンス力は鍛える必要があります。
短期で身につくことも多いのがこの能力なのかな、と思っています。
毎日の実践の場が一番
実践し続けてエラーを拾っていく。これが、それ以上ない技術が身に付く方法です。
エジソンも「私は失敗した事がない。ただ、1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ」と言っていますよね。
とにかく最速でトライを繰り返し、エラーを拾って修正していく、これ以上に最短の方法はないのだと思います。
なので事業所では毎朝5分の知識披露の場があります。自分の知っているジャンルについて話すことを最初は行ってから、介護保険制度や最近出会った疾患についての学びなど様々です。
各々の発達段階に合わせて課題として毎週課すこともありますが、突発的にこのジャンルなら話せるのではと前日、当日に話を振ることもあります。
そうしてみて「分かったつもり」であった知識が、そもそも相手との前提の土俵が異なっていたり、質問を受けてみると、そこ考えたことなかったなと感じたり、逆に質問がないと「あれ?本当に分かってもらえたのかな」と不安になったりとたくさんの気づきがあります。
在宅でのパフォーマンスの場はいつも突然です。先生からのお話があります、その後看護師が理解できたかを確認します、ではなく、訪問の時に突然「これってどうしたら…」、電話がかかってきて「今こんなことがあったんですが」など意表をついたタイミングで来ることもしばしば。
なので「そう言う時になったら準備しよう」では遅いんです。いつもその状況に備えておかなければいけない。でもそれは知識も重要ですが、真剣に話を聞いてくれた、分かってもらえた、真摯にアドバイスをくれた、そう相手が感じるパフォーマンスができるか、それもとても大切です。
そんな大切な機会を事前に事業所で迎えておく、それができる教育なのかな、と思っています。
そんな私の根拠のない、教育のトライのお話、でした。
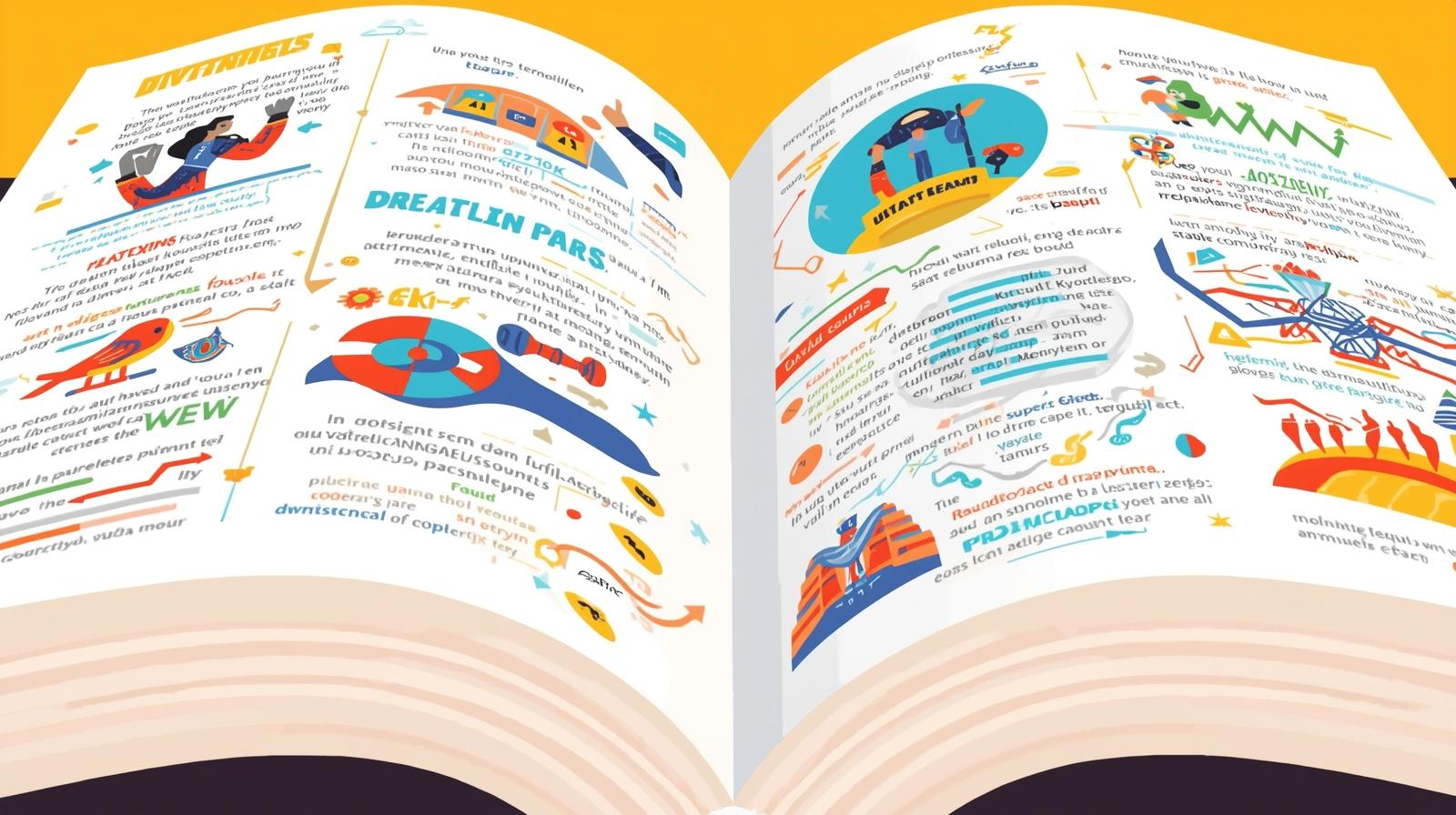
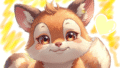

コメント